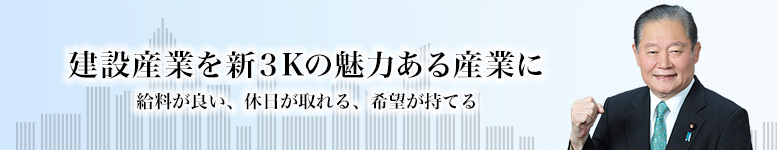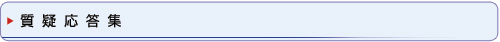
第217回国会 参議院 予算委員会 議事録
2025年3月17日(月)
佐藤信秋君
ということで、どういう再建の仕方をするかということを今更に打合せしながらやっていただいているということでありますので、これもまたある程度この調査、計画が進みましたら総理の方で果断なる御決断をお願い申し上げたいと、今はお願いだけに申し上げておきます。ありがとうございます。
そこでなんですよね。いろいろ災害が起きますと、去年の輪島なんか典型ですけど、あれ二十年ほど前に地震を受けて、それで実は地元のこの建設関係者も六割ぐらいになっているんですよ、それ以来、その後でね。そういう中であれだけの地震災害と、こういうことなものですから、なかなかスムースにはいかないと、そういう面もあります。ただ、基本的には人口や産業の地方分散というのをもう一回やらなきゃいけないかな、地方創生二・〇というのは、総理、そのために頑張っていただいているのかな、こう思います。
実は、本当はデータを用意すりゃいいんですけど、何分明治の、明治の二十年でしたかね、明治十三年に日本帝国の最初の統計年鑑というのを出したんですね。そのときに、総理御存じだと思いますけど、全国で前は四十だった、四十、都道府県一緒になったりしていまして、その後分かれたんですけど、あるいは一緒になったり、分かれたり。
島根県は、人口ではそのときに、何と島根、鳥取、プラス鳥取なんですよ、そのときは百四万人、百四万人。全国が三千六百万人ぐらいの頃ですから。百四万人。石川県が一番、今も能登、能登のあの石川県が一番人口としては多くて、ただし、これは富山と福井とが一緒と、こういう問題でもありましたから、それにしても圧倒的に多かった、石川県が。東京はというと、東京、十七番、九十五万人ね。そこから今みたいなこの集中が出てきているわけですけどね。
国税も、これはちょっとはっきりしないところあるんですけど、国税、税金払う分ね、それぞれの地域別でいうと、実は東京では二・五%、国税の二・五%。これは、それこそ島根とか石川とか和歌山とか、結局一次産業ですから、が、主たる県が多く払った、こういうことであるんですね。結局、地方のそういう力を寄せ集めて結集して、財と人口も供給しながら、地方から、ということなんですね。で、東京から愛知、大阪までという富国強兵をやってきたと。
その結果が、戦後は、その勢いで結局、大都市と地方の分散がなかなかうまくいかない。元々、第一次の全国総合開発計画のときから過密過疎というのを問題にして、過密、多過ぎる人口のところと過疎のところと、そこをどう調整しようか、修正しようかと、こういう動きでやってきたわけですけども、ちょうど平成二十年になって国土形成計画と、全国総合開発計画はそういう、基本的にはいつも地方分権と、こういうふうにやってきたわけですね。それで、国土形成計画、平成二十年では、今から約二十年ほど前、国土形成計画ということで、魅力のある、特色のある地域づくりをやっていくこと、こういうふうにしました。
ただ、この頃は、日本という国は物すごく勢いよかったんです、まだね。その勢いがいいまま、全国で、あっ、世界で、GDPも二番でしたからね。ちょうど今から三十年ぐらい前でいくと、関東全体で中国の生産高、生産額とほぼ一緒だったんです。フランスとは、中部圏プラスアルファちょっとぐらいでフランスの生産高と一緒。日本は大変な経済的な優位な国でしたからね。
その後、随分変わってはきました。結局、効率第一ということで国土形成なんかをやろうとしたわけですけど、でも、総合開発というのはもういいじゃないかと。ただ、本当にそうだったかなと、こういう、私自身、自分でそこにタッチしながら反省もしたりしています。
しかしながら、大事なことは、これからどうやって雇用や教育を、教育、雇用を分散させながら地方の活力を出していってもらうか、これが大事なことだと思いますので、総理の地方創生二・〇という一生懸命おやりになっているライフワーク、総理のライフワークでもありますよね、ということで、その御決意をお願い申し上げたいと思います。
内閣総理大臣(石破茂君)
御指摘ありがとうございます。
私も、昭和三十年代、四十年代、鳥取で育ちました。NHKでもそうですが、明日の裏日本の天気はと言われてすっごい悲しかったことを覚えております。
委員御指摘のように、統計を取り始めて以来、日露戦争の辺りまでだったと思いますが、新潟県が大体全国の人口トップでした。時々石川が替わることがありましたが、どちらにしても日本海側がトップだった。で、裏日本という言葉が出てくるようになったのは、これも御指摘のとおりですが、東京の人口が新潟を抜いたときから裏日本と言われるようになりました。それまでは、日本海側を内日本と言っておって、太平洋側を外日本と言っておったはずでございます。
これをどうやってまた地域に活力を取り戻していくかということを考えたときに、もちろん人口をどうするかということもございます、若者や女性に選ばれる地方、産官学の地方移転と創生、地方イノベーションの創生構想、新時代のインフラ整備、広域リージョン連携と、こういうの、五つの柱を立てておるところでございます。
一昨日、私、長野県の伊那市あるいは宮田村というところに行かせていただいて、知事さんや市長さんや村長さんや地域の方々、随分長い時間お話をさせていただきました。あっ、こんなことがあるんだなっていうのは随分と気付きがありました。
幸せの青い車って言うんだそうですが、青いバン、ボックスカーみたいなものでしょうか、そこに看護師さんが乗って訪問介護をすると。お医者さんとはデジタルでつないで、そこにおいて医師の指示の下にいろいろな行為が行われるというようなこと、随分と効率が上がったそうです。頻度も増した、お医者さんの負担も減ったということでございます。あるいは移動のオフィスのようなもの、それも車の中にいろんなものがあって、六人寝泊まりできるような、そういう車の活用がございました。あるいはドローンと言うのかどうか分かりませんが、かなり大型の無人ヘリがいろんな物が運べるようになるというようなことでございます。あるいはCCRCと申しますが、地域でいろんな方、高齢者の方と、看護される、介護される方とする方だけではなくて、赤ちゃんもいっぱいいる、ちっちゃな子供たちもいっぱいいる、高齢者の方もいっぱいいる、みんなでそこでコミュニティーつくろうよっていうような取組、いろんな取組が地方から始まっているということでございます。
その地域のことはその地域でなきゃ分かりません。霞が関で全部分かるわけではございません。地方創生の人材もこれから更に派遣をするようにいたします。本当に一緒にやろうよと、国と地方が力を合わせて一緒にやろうよという、そういう熱気をもう一度取り戻していきたいと思っております。必ずそうすることによって地域に活力が取り戻せるということで、もう人口が減るからどうにもならないなということではなくて、どうやって地域地域にもう一度活力を取り戻すかということについて、国として可能な限りの支援を行い、地方創生というものを実現したいと考えておるところでございます。
佐藤信秋君
ありがとうございます。
そこで、時間も大分迫ってきましたけど、実は、長いこと私も、こちらの参議院に出るときに、つくづくこれが大事だというんで、私の当時やっていた仕事の延長以外のことで申し上げたのが、医師の偏在直そうと、なくそうと、それにはふるさと医学部というのが必要だなと、こういう公約をさせていただいて、ふるさとの大学に行く若者たちと、それから通常のそれまでの枠と、そもそも入学枠から少しふるさと用の枠つくったらいいじゃないかということでやっていただいてきたつもりでいます。
今どういう状況にあるか、人数がですね、よろしくお願いします。
国務大臣(あべ俊子君)
佐藤委員にお答えさせていただきます。
また、委員には、東日本大震災のときにも、自民党が野党であったときに、本当に的確なアドバイスをいただきましたこと、心から感謝申し上げまして、本当に安全で美しいふるさとをつくるということで、本当に頑張ってこられた委員、尊敬するわけでございまして、そうした中でお答えさせていただきます。
この令和六年度の医学部入院定数が、定員が九千四百三名のうち、地域の医師確保等を目的とするいわゆる地域枠等の定員は一千八百八名でございます。
佐藤信秋君
ということで、随分増やしてきていただいたというのがこの資料四見ていただくと分かると思います。ただ、もっと増やしていただきたいと、まあまあそういうことなんですけどね。
そして、結局、このお医者さんの、医師の偏在の問題は、もう一つの問題として、医師の報酬の問題があります。結局、全国一律ですからね、医療報酬というのはね、だから、診療報酬は、ですから、なかなか患者の少ない地方ではやっていきにくいと、こういう問題があるというふうにも伺っております。
あわせまして、この偏在是正を図るためには、患者さん少ないんですからね、どっちかいえば、そうすると、患者の負担はできれば減らしながら医師の報酬そのものは上げていくと、地方のお医者さんをですね、それも大事なことだと思いますんで、あわせまして、厚労大臣にお願いします。
国務大臣(福岡資麿君)
御指摘ございましたように、医師の地域の偏在の是正、これは、将来にわたって地域で必要な医療提供体制を確保する上で大変重要な課題だというふうに認識しております。
このため、昨年末に医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージというものを策定いたしまして、国会に医療法等改正法案を提出をさせていただいたところです。この中で、都道府県において重点的に医師を確保すべき区域を設定させていただいた上で、御指摘ありましたように、経済的インセンティブの一つといたしまして、この区域に勤務するお医者さんに手当を支給する事業を実施することを検討してございます。
また、医師の人件費は本来診療報酬により賄われるものでございますが、特定の地域に対して診療報酬で対応した場合、当該地域における患者負担の過度な増加を招くおそれがありますことから、検討中の事業におきましては、全ての被保険者に広く御協力いただく形で、保険者の拠出金により対応することとさせていただいております。また、この事業の実施が医療給付費や保険料の増加の原因とならないようにする形で、診療報酬改定において一体的に確保することとさせていただきたいと考えております。
保険あってサービスなしという地域が生じないよう、引き続き、地方自治体、医療関係者、保険者等と連携しながら、地域の実情に応じた実効ある医師偏在対策を進めていきたいと思います。
佐藤信秋君
ありがとうございました。
いろんなことをやりながら地方、国土の強靱化というのはやっていかなきゃと、今のようなお話も含めてですね。
で、総理の方には、国土の強靱化に対してこれからどう取り組んでいただけるかということを、是非、時間がなくなりましたので、これから総理にそこの点をお伺いしたいと思います。
内閣総理大臣(石破茂君)
委員の御指導いただきまして、防災・減災、国土強靱化は災害に強い交通ネットワークへ転換していかねばならない。もう一つは、予防保全型の老朽化対策というものに本格転換をしていかねばならないと思っております。
御指摘のように、投資への波及効果も含めた経済効果というものが期待をされます。令和八年度からの国土強靱化実施中期計画につきまして、おおむね十五兆円程度の事業規模で実施中の五か年加速化計画を上回る水準が適切と考え方に立っておりまして、必要な対策を積み上げ、本年六月をめどに策定をいたします。
佐藤信秋君
ありがとうございます。
十五兆円の規模を上回る、事業の規模を上回る。実は、私自身は、結局、物価が上がっていますから、建設物価も諸物価も上がっています。そうすると、十五兆円の投資の規模というのはというので私自身が大変期待していますのは、投資の規模は結局事業の量と、金額ではなくてですね、ということで、同じ百メートルの堤防を造るにはちょっと金がかさむようになってきていますし、そのKPIを同じにすると、こういうことを総理はお考えいただいて、あえて事業の規模と言ったと、こういうことだと思っていますんで、どうぞよろしくお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
ありがとうございました。
内閣総理大臣(石破茂君)
以上で佐藤信秋君の質疑は終了いたしました。(拍手)